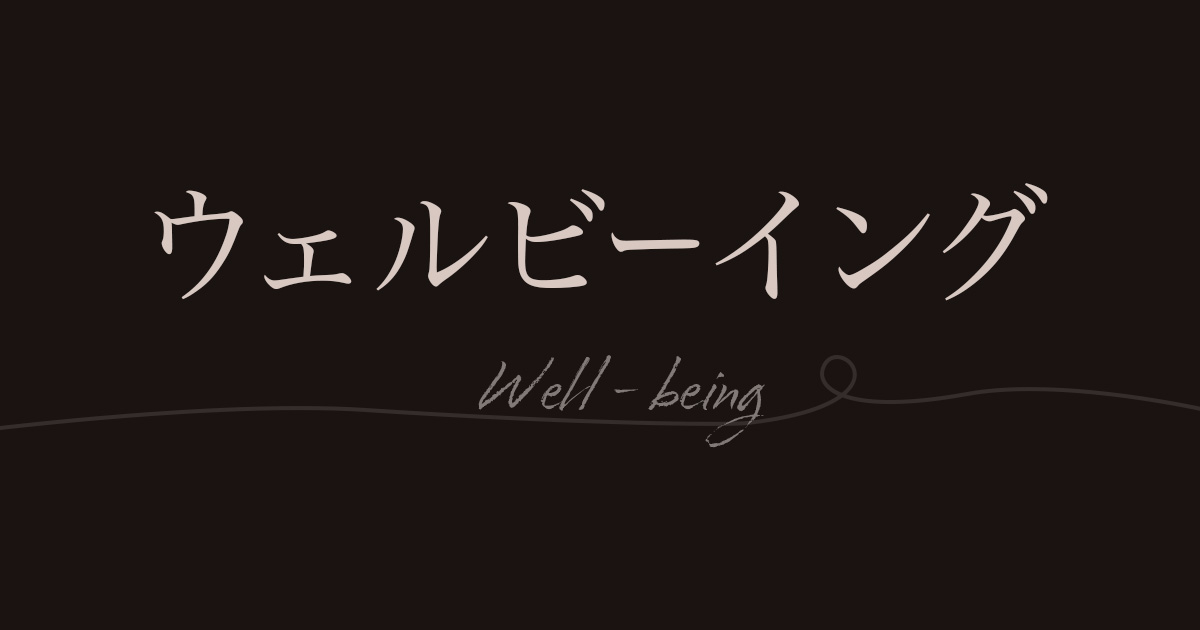最近、よく耳にするウェルビーイング(Well-being)。一大ムーブメントとして、国や自治体、民間企業、大学などでも積極的に取り入れられていますが、今ひとつピンと来ないですよね。
ここでは、ウェルビーイングの定義や注目される背景、私たち個人個人がどのように「幸福」を測れるのかを詳しく解説します。
ウェルビーイングとは?
ウェルビーイングとは、心身ともに良好な状態にあることを意味する概念で、日本語では「幸せ」「幸福」と訳されることもあります。意味を聞けば何となく理解できたつもりになるものの、一体どのような定義であり、なぜ注目されているのでしょうか?
それぞれ順に解説します。
WHOが最初に触れたウェルビーイングの定義
ウェルビーイングは、直訳するとwell(よい)とbeing(状態)。この言葉が初めて登場したのは1946年の世界保健機関(WHO)設立時。世界保健機関憲章で「健康」を定義する際、ウェルビーイングという言葉に触れました。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
参照:世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。
つまり、ウェルビーイングは単に「幸せ」「幸福」を感じるだけでなく、心身の健康、良好な人間関係、充実した生活など、様々な要素を含む言葉だということがわかりました。
同じ幸せ?happinessとwell-beingの違い
HappinessとWell-beingは、どちらも日本語では「幸せ」と訳されますが、実は微妙な違いがあります。
Happinessは、瞬間的な喜びや幸福感を指します。例えば、美味しいものを食べたり、好きな人と会ったり、目標を達成したりした時に感じるような、一時的な高揚感です。
一方、Well-beingは、心身ともに良好な状態を指します。これは、単に幸せを感じるだけでなく、身体的にも精神的にも健康で、充実した生活を送れていることを意味します。
ウェルビーイングが注目される背景
国や民間企業に取り入れられるなど、ウェルビーイングが注目される背景には様々な理由があります。
それぞれ順に解説します。
価値観の多様化
近年、人々の価値観は多様化しており、物質的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視する人が増えています。
ウェルビーイングは、物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさも重要であるという考え方です。自分自身の人生に意味や目的を見出し、充実感を感じることがウェルビーイングにとって重要です。
SDGs 17の目標を達成するため
ウェルビーイングとSDGs(持続可能な開発目標)は、一見すると異なる概念のように思えますが、実は密接に関係しています。世界の誰一人取り残さない社会のための17の目標の中には、ウェルビーイングに直接関係するものがいくつかあります。
これらの目標は、すべての人が心身ともに健康で、充実した生活を送れるようにするためのものであり、ウェルビーイングの理念と一致しています。また、SDGsの達成は、ウェルビーイングの向上にもつながります。例えば、貧困の撲滅や教育の普及、ジェンダー平等の実現などは、すべての人々のウェルビーイングを向上させるための重要な要素です。
働き方改革の推進
近年、長時間労働や過重労働の問題が深刻化し、働き方改革が推進されています。長時間労働は、従業員の健康を損ない、生産性の低下にもつながることが分かっています。
ウェルビーイングは、従業員の心身の健康とワークライフバランスの向上を重視する考え方であり、働き方改革と密接に関係しています。ウェルビーイングを意識した働き方改革を進めることで、従業員のモチベーションや生産性の向上が期待できます。
教育現場でも注目されている
近年、子どもたちが抱える困難は多様化と複雑化が進んでいます。いじめや不登校、虐待、貧困、学習障害など、様々な問題を抱える子どもたちが増えています。
ウェルビーイングは、子どもたちの心身の健康を向上させるための有効な方法として期待されています。ウェルビーイングを高めることで、子どもたちはストレスや不安に上手に対処できるようになり、自己肯定感やレジリエンス(困難を乗り越える力)を身につけることができます。
識者が創設した4つのウェルビーイング
ウェルビーイングには様々な研究があります。ここでは代表的な理論やアプローチを紹介します。
それぞれ順に解説します。
セリグマン博士の「PERMA(パーマ)」モデル
PERMAモデルは、アメリカのポジティブ心理学の創始者であるマーティン・セリグマン博士が提唱した、ウェルビーイングを構成する5つの要素のモデルです。
PERMAは、以下の5つの英単語の頭文字を取ったものです。
- P:Positive Emotion(ポジティブ感情)
- E:Engagement(没頭・熱中)
- R:Relationships(人間関係)
- M:Meaning(人生の意味)
- A:Achievement(達成感)
PERMAモデルでは、これらの5つの要素が相互に関連し合い、ウェルビーイングを高めるために重要であると考えられています。
ギャラップ社の「主観的ウェルビーイング」
米ギャラップ社は、世界規模の調査会社として知られています。同社は、主観的ウェルビーイングを5つの要素で構成される概念として定義しています。
5つの要素は以下の通りです。
- Career well-being:仕事にやりがいを感じ、成長していると感じる状態
- Social well-being:良好な人間関係を築いており、社会の一員として認められていると感じている状態
- Financial well-being:経済的な安定を確保しており、将来への不安を感じていない状態
- Physical well-being:身体的に健康で、病気やケガがない状態
- Community well-being:地域社会に貢献していると感じ、地域の一員としてつながりを感じている状態
ギャラップ社は、これらの5つの要素を調査し、世界各国の主観的ウェルビーイングの比較分析を行っています。
シャハー博士の「SPIRE」アプローチ
SPIREアプローチは、アメリカのポジティブ心理学の研究者であるタル・ベン・シャハー博士が提唱した、ウェルビーイングを高めるための実践的なフレームワークです。
SPIREは、以下の5つの英単語の頭文字を取ったものです。
- S:Spiritual Well-being:自分の人生に意味や目的を見出し、価値観に基づいて行動すること
- P:Physical Well-being:健康的な生活習慣を送り、心身ともに健康な状態を維持すること
- I:Intellectual Well-being:学び続けること、新しいことに挑戦すること、創造性を発揮すること
- R:Relational Well-being:良好な人間関係を築き、社会の一員としてつながりを感じる
- E:Emotional Well-being:自分の感情を理解し、コントロールすること、ストレスに対処すること
SPIREアプローチでは、ウェルビーイングは5つの要素が相互に関連し合い、影響を与え合っていると考えられています。SPIREの5つの要素をバランス良く 高めることで、持続的なウェルビーイングを実現することができます。
前野隆司教授の「幸せの4つの因子」
前野隆司氏は、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授兼、武蔵野大学ウェルビーイング学部長・教授であり、幸福学の第一人者として知られています。前野氏は、幸福を科学的に研究し、幸せの4つの因子を提唱しています。
幸せの4つの因子は以下の通りです。
- やってみよう因子:夢や目標に向かって、主体的に努力を続けられる人ほど、幸せになれる
- ありがとう因子:周りの人や物に感謝の気持ちを持つ人ほど、幸せになれる
- なんとかなる因子:物事に前向きに取り組む人ほど、幸せになれる
- ありのまま因子:自分自身をありのままに受け入れ、自分らしく生きる人ほど、幸せになれる
前野氏によると、この4つの因子をバランス良く育むことで、幸福度を高めることができるといいます。
ウェルビーイングって測ることができる?
ここまでウェルビーイングの概要や様々な手法について学びました。しかし、今自分が満たされているのかどうかわかりやすく確認できるのでしょうか?ここでは自分のウェルビーイング度が数値でわかる方法をお伝えします。
それぞれ順に解説します。
世界幸福度ランキング
世界幸福度ランキングは、国連大が毎年発表しているランキングです。140以上の国々を対象に、主観的な幸福度を調査し、ランキングしています。
前述したギャラップ社の調査をベースに、各国の約1,000人に「最近の自分の生活にどれくらい満足しているか」を尋ね、0(完全に不満)から10(完全に満足)の11段階で答えてもらう方式で国ごとの幸福度を測定。調査には、生活満足度、健康、自由、寛容性、信頼、所得、支援、期待寿命、寛容性などの要素が用いられています。
世界幸福度ランキングは、各国の幸福度を比較する指標として広く利用されています。2024年のランキングでは、フィンランドが7年連続で1位を獲得しました。日本は前回の47位から4つ下げて、143カ国中51位でした。
- フィンランド 7.741
- デンマーク 7.583
- アイスランド 7.525
- スウェーデン 7.344
- イスラエル 7.341
- オランダ 7.319
- ノルウェー 7.302
- ルクセンブルク 7.122
- スイス 7.060
- オーストラリア 7.057
………
51. 日本 6.060
※数字は幸福度スコアを表す
世界幸福度ランキングは、主観的な幸福度を測る 指標として一定の参考価値はありますが、完璧な指標ではないという批判もあります。
キャントリルの梯子
キャントリルの梯子は、主観的な幸福度を測定するために用いられる心理尺度です。1965年にカナダの心理学者ロバート・キャントリルによって開発されました。
梯子には0から10までの11段があり、0は最悪の人生、10は最高の人生を表しています。回答者は、自分の人生が梯子のどの段に位置すると感じるかを評価します。
キャントリルの梯子は、世界幸福度ランキングなどの国際的な調査で広く利用されています。また、個人のカウンセリングや職場での幸福度調査などにも活用されています。
人生満足度尺度
幸福感研究の第一人者であるエド・ディナー教授らが開発した「人生満足度尺度(SWLS)」は、幸福感を測定する代表的な尺度として広く用いられています。
この尺度は、以下の5つの質問で構成されています。
- ほとんどの面で、私の人生は私の理想に近い
- 私の人生は、とてもすばらしい状態だ
- 私は自分の人生に満足している
- 私はこれまで、自分の人生に求める大切なものを得てきた
- もう一度人生をやり直せるとしても、ほとんど何も変えないだろう
各質問には、1点(全くそう思わない)から7点(とてもそう思う)までの7段階評価を当てはめ、5つの点数を合計します。
幸福度診断(Well-Being-Circle)
Well-Being Circleは、株式会社はぴテックが提供する、幸福度を多角的に測定するサービスです。前述の前野隆司教授と共同開発されており、72問のアンケートに答えることで、34の項目にわたってあなたのウェルビーイングを調べることができます。
ウェルビーイングとは、単に「幸せ」であることだけでなく、心身の健康、人間関係、仕事、生きがいなど、人生の様々な側面における充実感を総合的に指したものです。Well-Being Circleでは、ポジティブ心理学に基づいた質問項目を用いることで、主観的な幸福感だけでなく、客観的な幸福指標も測定することができます。
まとめ
ウェルビーイングに正解はなく、人によって様々な意味を持ちそうです。これは「一人ひとりが自分らしく生きること」と言い換えられるかもしれません。
国や自治体でも、ウェルビーイング指標の開発・導入、調査・研究、情報発信、官民連携など、ウェルビーイングの向上に向けた取り組みを積極的に進めています。
自分自身や子供たち、そして社会のために、一緒に考えていくきっかけとしてみてはいかがでしょうか?